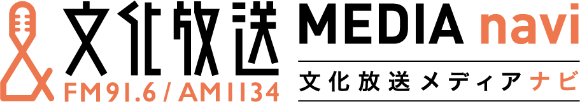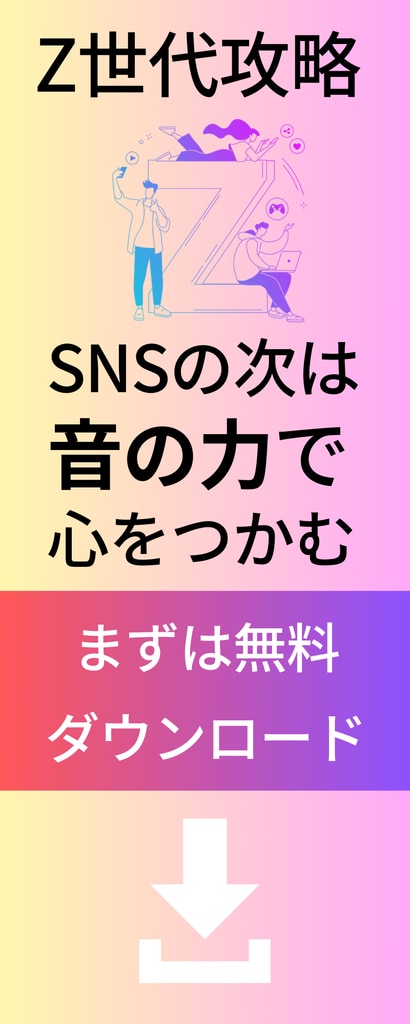【広告主必見】ブランドセーフティとは?事例や対策方法を解説
デジタル広告の普及に伴い、ブランド毀損リスクがかつてないほど高まっています。不適切なコンテンツや信頼性の低いサイトに広告が表示されることで、企業のブランド価値が損なわれるケースが後を絶ちません。このようなリスクを回避し、広告効果を最大化するために不可欠なのが「ブランドセーフティ」です。本記事では、ブランドセーフティの基本概念から実際に問題になった事例、広告プラットフォームを含む、各組織の取り組みまで詳しく解説します。企業のマーケティング担当者や広告運用者にとって、デジタル広告戦略の根幹を支える重要な知識となるので、ぜひご覧ください。
目次[非表示]
- 1.ブランドセーフティとは
- 2.ブランドセーフティの重要性
- 3.ブランドセーフティが問題になった事例5選
- 3.1.①イギリス政府
- 3.2.②ユニリーバ・ジャパン
- 3.3.③P&G
- 3.4.④資生堂
- 3.5.⑤ネスレ
- 4.6つの組織におけるブランドセーフティへの取り組み
- 4.1.①JIAA(日本インタラクティブ広告協会)
- 4.2.②JAA(日本アドバタイザーズ協会)
- 4.3.③Meta(旧Facebook)
- 4.4.④X(旧Twitter)
- 4.5.⑤YouTube(Google)
- 4.6.⑥LINEヤフー
- 5.ブランドセーフティ対策3選
- 5.1.①ホワイトリスト・ブラックリスト
- 5.2.②PMP(プライベートマーケットプレイス)
- 5.3.③アドフラウド対策ツール
- 6.まとめ
ブランドセーフティとは
ブランドセーフティとは、企業の広告が不適切なコンテンツやサイトに掲載されることを防ぎ、ブランドイメージを守るための取り組みを指します。デジタル広告市場の拡大とともに、広告の配信先を広告主が完全にコントロールすることが難しくなっており、ブランド毀損のリスクが高まっています。
例えば、暴力的・扇動的なニュースサイトやフェイクニュースを扱うメディアに広告が掲載されることで、消費者が企業の価値観に疑問を持つケースが発生します。また、アダルト・ギャンブル・違法薬物関連のコンテンツと並んで広告が表示されることで、ブランドの信頼性が損なわれるリスクもあります。
広告配信の自動化が進む中、ブランドセーフティ対策を怠ると、意図せず問題のあるサイトに広告が掲載され、企業の評判を傷つけるだけでなく、違法・反社会的な勢力に広告費が流れる可能性もあります。広告主は単なるクリック率やコンバージョン率の向上だけでなく、広告がどこに表示されているのかを正確に把握し、ブランドイメージを守る戦略的な広告運用を行う必要があります。
ブランドセーフティの定義
ブランドセーフティは、広告が不適切なコンテンツや環境に掲載されることを防ぎ、企業のブランド価値を守るための取り組みです。特にデジタル広告においては、プログラマティック広告の普及により広告配信の管理が複雑化しており、企業が意図しない掲載面で広告が表示されるリスクが高まっています。
業界団体による定義を見てみると、日本インタラクティブ広告協会(JIAA)は「広告掲載先の品質確保による広告主ブランドの安全性」とし、日本アドバタイザーズ協会(JAA)は「ブランドを毀損する不適切なページやコンテンツに広告が表示されるリスクから、安全性を確保する取り組み」と定義しています。また、一般社団法人デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)も「広告掲載先の品質確保による広告主ブランドの安全性」と述べており、いずれも広告の掲載面に対する視点が強調されています。
ブランド適合性(Brand Suitability)との違い
ブランドセーフティと混同されがちなのがブランド適合性(Brand Suitability)です。ブランドセーフティが「不適切なコンテンツへの広告掲載を防ぐ」ことを目的とするのに対し、ブランド適合性は「自社のブランドイメージに合うコンテンツに広告を配信する」ことを指します。ブランド適合性を確保するには、ブランドイメージの調査・分析やターゲットの明確化が不可欠です。ブランドセーフティが最低限のリスク回避を目的とするのに対し、ブランド適合性は広告効果の最大化を目指す点で異なります。
ブランドセーフティの重要性
ブランドセーフティが求められる背景には、デジタル広告の自動化と配信先の不透明性があります。従来の広告は特定の「枠」に出稿されていましたが、運用型広告の普及により「人」をターゲットに配信されるようになり、広告主が掲載先を完全にコントロールすることが難しくなりました。その結果、広告が意図せず暴力的・扇動的なサイトや違法コンテンツと並んで表示され、ブランド毀損のリスクが高まっています。これにより、消費者からの信頼低下、誤ったブランドイメージの定着、さらには反社会的勢力への広告費流出といった問題が発生します。ブランドセーフティを確保することで、広告主はブランド価値を守り、適切な広告配信を通じて信頼を維持できます。単なる広告効果向上だけでなく、企業の社会的責任(CSR)や長期的なブランド戦略においても、ブランドセーフティは不可欠な要素となっています。
ブランドセーフティが問題になった事例5選
①イギリス政府
2017年、イギリス政府の選挙広告がYouTubeのイスラム過激派動画に配信され、広告収益が過激派の資金源となる事態が発生しました。この問題は「政府が過激派を支援している」との批判を招き、ブランド毀損リスクの深刻さを浮き彫りにしました。同年3月には、英タイムズ紙の報道を受け、世界的広告会社アバスがGoogleおよびYouTubeへの広告出稿を全面停止。これを機に、多くの企業がYouTube広告のブランドセーフティ対策を強化しました。この事例は、広告主が配信先を正確に管理できないリスクを象徴しており、ブランドセーフティの重要性が改めて認識される契機となりました。
②ユニリーバ・ジャパン
2017年、ユニリーバ・ジャパンの広告が、特定の暴力的コンテンツや政治的主張を含む番組に自動配信され、SNS上で批判が殺到しました。広告主が意図しない形で政治的・社会的メッセージと結びつくリスクが浮き彫りになり、メディアでも大きく報道される事態に発展。ユニリーバ・ジャパンは即座に広告出稿を停止し、配信管理体制の見直しを発表しました。このケースは、広告配信の自動化が進むなかで、ブランドセーフティ対策の不備が企業のブランド価値を損なう可能性があることを示した代表的な事例です。
③P&G
2017年、IAB(インタラクティブ広告業界団体)のカンファレンスで、P&Gの最高ブランド責任者マーク・プリチャード氏が、デジタル広告の透明性向上を強く訴えました。広告価値の毀損に対する警鐘を鳴らし、アドフラウドやブランドセーフティの重要性を指摘。併せて、P&Gは透明性の低いメディアとの取引を見直す方針を発表しました。このスピーチは業界全体に大きな影響を与え、アドベリフィケーションの概念が広く認知される契機となりました。ブランドセーフティ対策の必要性が、広告主だけでなく業界全体に浸透するきっかけとなった重要な事例です。
④資生堂
資生堂はブランドイメージを守るため、2018年から全社的にブランドセーフティ対策を強化。ホワイトリストやブランドセーフティツールを導入し、広告出稿先の安全性を厳格に管理しました。確実に安全なサイトにのみ出稿する方針を明言し、数値分析を活用して出稿先の整理を実施。この取り組みは、ブランド毀損リスクを排除し、広告効果を最大化する成功事例の一つとして注目されています。
⑤ネスレ
ネスレは2016年からデジタル広告の安全性向上に取り組み、スイス本社で「ビューアビリティ」「アドフラウド」「ブランドセーフティ」の3項目に関するガイドラインを策定。同年10月から日本でも実施を開始しました。広告が閲覧されるだけでなく、ブランド価値を損なわないかを重視する方針を確立し、デジタルメディアの品質向上に貢献。ブランド毀損リスクを最小限に抑える取り組みとして注目されています。
6つの組織におけるブランドセーフティへの取り組み
①JIAA(日本インタラクティブ広告協会)
JIAA(日本インタラクティブ広告協会)は、デジタル広告業界における信頼性や品質向上を目指す団体です。同協会はブランドセーフティの確保に向け、広告主、媒体社、代理店がリスクを回避するための指針として「ブランドセーフティガイドライン」を策定しました。また、「デジタル広告品質認証制度」を運用し、広告配信環境の透明性を高め、安全性の高い広告取引を促進しています。さらに、アドベリフィケーション技術の活用を推奨し、不適切なコンテンツへの広告掲載を防ぐ取り組みも行っています。これらの活動を通じて、JIAAは業界全体でブランドセーフティを強化し、広告の信頼性向上を目指しています。
②JAA(日本アドバタイザーズ協会)
JAA(日本アドバタイザーズ協会)は、日本の広告主を代表する業界団体です。広告主の利益を守るために活動しており、ブランドセーフティの重要性を認識し、広告主が広告掲載先のリスクを最小限に抑えるための取り組みを行っています。具体的には、広告主が不適切なコンテンツに広告が掲載されるリスクを避けるため、適切な基準やガイドラインを設け、メディアや広告配信プラットフォームと連携してブランドセーフティを確保しています。また、広告主への教育や啓発活動を通じて、ブランドセーフティの重要性を広める活動も行っています。
③Meta(旧Facebook)
Metaは「Facebookコミュニティ規定」を定め、不正や有害なコンテンツを防ぐためにさまざまな取り組みを行っています。具体的には、新しいブランドセーフティおよび適合性ツールを導入し、フィードやリール用のコンテンツブロックリストコントロールやサードパーティ機能を強化。さらに、事前検知技術や35,000人以上のスタッフによる審査を通じて、ヘイトスピーチやいじめなどの有害なコンテンツを削減しています。2024年には、ヘイトスピーチの表示頻度を80%以上減少させ、自殺や自傷行為に関するコンテンツの99.1%をAIによって事前に検知しました。
④X(旧Twitter)
X (旧Twitter)は「ブランドセーフティに関するXポリシー」を策定しています。具体的な取り組みとしては、広告主が配信内容を管理できる複数の機能を提供しています。これには、特定のコンテンツやキーワードを除外したり、広告の配信先を管理したりする機能が含まれます。また、センシティブなコンテンツと広告の隣接を避け、機械学習と人的審査を組み合わせて不適切な広告配信を防止しています。さらに、Amplifyプログラムではパートナーに対し、基準に沿ったコンテンツを収益化するための教育とサポートも行っています。
⑤YouTube(Google)
YouTubeは「広告掲載に適したコンテンツのガイドライン」を策定し、広告掲載のルールや広告掲載に適さないコンテンツについて明示しています。ほかにも、広告主がコンテンツカテゴリーを基に広告を調整できる機能を提供。また、AIと人間の審査員が、不適切なコンテンツ(ヘイトスピーチや暴力を助長する内容など)を検出・削除することで、広告が安全なコンテンツに表示されるようにしています。
⑥LINEヤフー
LINEヤフーは、「広告配信ガイドライン」を策定し、広告主が設定した基準に基づいて広告配信先を管理し、不適切なコンテンツを回避するための監視体制を整備しています。具体的には、人とシステムによるパトロールにより、広告と不適切なコンテンツの誤配信を防止する取り組みを行っています。また、リアルタイム検知システムを活用して、ユーザーによる誹謗中傷といった書き込みも24時間常時検知し、不適切と判断されたコンテンツは即座に広告配信をブロックしています。ほかにも、ブラックリスト・ホワイトリストの作成やアドベリフィケーションベンダーを用いた第三者計測を行い、配信先をコントロールしています。
ブランドセーフティ対策3選
①ホワイトリスト・ブラックリスト
ホワイトリストとブラックリストは、ブランドセーフティの基本的な対策として非常に有効です。ホワイトリストは信頼性の高いサイトのみを選定して広告配信することで、不適切なサイトへの広告配信リスクを減少させます。反対に、ブラックリストは不適切なサイトやコンテンツを選定して広告配信を制限します。ただし、ホワイトリストに絞ると広告単価が上がり、ブラックリストは新たに出現する不適切なサイトを常に更新し管理する必要があります。
②PMP(プライベートマーケットプレイス)
PMP(プライベートマーケットプレイス)は、信頼性の高いメディアと広告主に限定して広告配信を行う仕組みです。DSPと異なり、PMPは事前にベンダー審査を通過したメディアのみを使用するため、ブランド毀損のリスクを軽減できます。また、広告がどのメディアに配信されるかが把握しやすく、透明性の高い広告運用が可能です。
③アドフラウド対策ツール
アドフラウド対策ツールは、広告がブランドに適合した媒体に掲載されているか、不適切な形で表示されていないかを確認・検証するツールです。これにより、ブランド毀損のリスクがあるサイトや特定のキーワードを含むコンテンツへの配信をブロックできます。効率的なブランドセーフティ対策を実施でき、広告配信先が適切かどうかや、表示方法を分析することが可能です。
まとめ
ブランドセーフティは、ブランドイメージを守るために広告配信先を適切に選定する重要な取り組みです。不適切なサイトへの配信は、信頼低下やブランド毀損を招く可能性があるため、ホワイトリストやブラックリスト、PMP(プライベートマーケットプレイス)などの対策が有効です。また、アドフラウド対策ツールを活用することで、効率的にブランドセーフティを実現できます。広告主はこれらの対策を講じることで、信頼性の高い広告運用が可能になります。