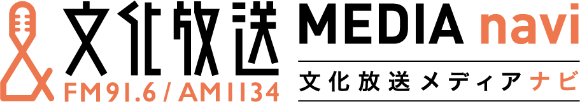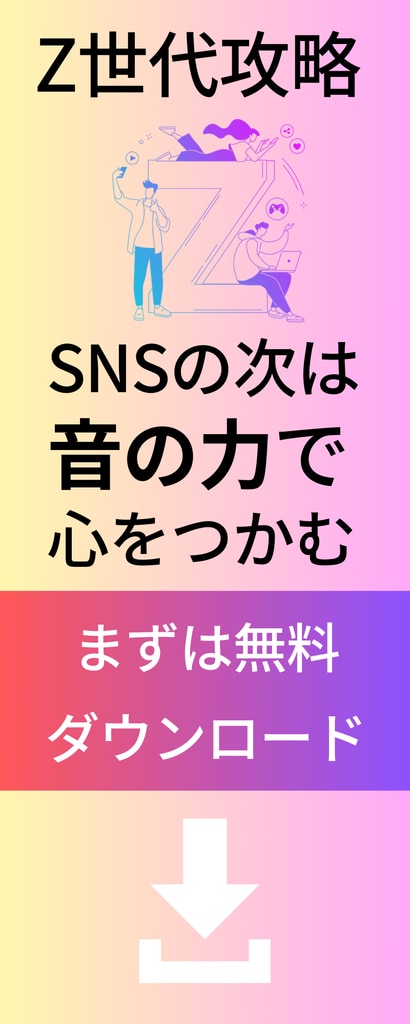【貴社の広告は大丈夫!?】アドフラウドとは?広告詐欺13種類と4つの対策を解説
デジタル広告市場の急成長とともに、その裏側で進行している「アドフラウド(広告詐欺)」の問題は、年々深刻さを増しています。特に日本では、被害額が数千億円にものぼると言われ、広告主にとっては無視できないリスクとなっています。しかし、広告詐欺の手法やその対策を理解している企業は少なく、依然として多くの企業が被害に気づかぬまま広告費を浪費しています。
本記事では、アドフラウドの概要を解説したうえで、実際に用いられている13種類の詐欺手法を詳述し、企業が講じるべき4つの具体的な対策方法を紹介します。これらを踏まえることで、無駄な広告費を削減し、効率的なマーケティング投資が可能となります。今後の広告運用におけるリスク回避のため、必ず押さえておきたい知識をお伝えします。
目次[非表示]
- 1.アドフラウドとは
- 1.1.アドベリフィケーションとは
- 1.2.ブランドセーフティとは
- 1.3.ビューアビリティとは
- 2.アドフラウドの仕組み
- 3.アドフラウドが広告主に与えるデメリット
- 4.アドフラウドの種類13選
- 4.1.①隠し広告
- 4.2.②過度な広告領域
- 4.3.③広告スタッキング
- 4.4.④アドインジェクション
- 4.5.⑤クリック洪水
- 4.6.⑥ブラウザの自動操作
- 4.7.⑦自動リロード
- 4.8.⑧ドメインスプーフィング
- 4.9.⑨ファーム(デバイスファーム)
- 4.10.⑩デバイス乗っ取り
- 4.11.⑪データセンタートラフィック
- 4.12.⑫インストールハイジャック
- 4.13.⑬SDKスプーフィング
- 5.アドフラウド4つの対策
- 5.1.①正しい知識を身につける
- 5.2.②アクセスをモニタリングし、不自然な挙動に気をつける
- 5.3.③ホワイトリスト・ブラックリストを作成する
- 5.4.④アドフラウド対策ツールを導入する
- 6.まとめ
アドフラウドとは
アドフラウド(ad fraud)とは、Web広告における不正行為の総称で、ボットや詐欺サイトを活用して広告のインプレッションやクリック数を不正に操作し、広告費を詐取する手口を指します。アドフラウドは単なる金銭的損失にとどまらず、広告のパフォーマンスデータを歪め、最適な広告運用の判断を妨げるリスクも孕んでいます。広告主が意図しないユーザーや偽のトラフィックに予算を消費することで、正しいROI分析ができなくなるため、マーケティング戦略全体に悪影響を及ぼします。
アドフラウドは「アドベリフィケーション」の要素の一つです。アドベリフィケーションにはほかにも「ブランドセーフティ」「ビューアビリティ」の2つがあります。これらはアドフラウドには欠かせないもののため、以下で解説します。
アドベリフィケーションとは
アドベリフィケーション(Ad Verification)とは、広告が適切な環境で配信されているかを検証するプロセスのことです。具体的には、広告が不正なクリックやインプレッションの対象になっていないか(アドフラウド)、ブランドのイメージを損なうサイトに掲載されていないか(ブランドセーフティ)、ユーザーに実際に視認されているか(ビューアビリティ)の3つを確認します。DSPやアドネットワークの普及により、広告配信の自動化が進んだ一方で、広告主が配信先を完全に把握できないケースが増えました。そのため、アドベリフィケーションを活用して、広告が適切な掲載先で正しく配信されているかをチェックすることが重要になっています。
ブランドセーフティとは
ブランドセーフティとは、企業の広告が不適切なコンテンツや環境に掲載されるのを防ぎ、ブランド価値を守る取り組みです。プログラマティック広告の普及により、広告主が配信先を完全に把握できないリスクが高まっています。暴力的・フェイクニュースサイトなどに広告が表示されると、消費者に誤った印象を与え、ブランド毀損につながる可能性があります。そのため、適切な掲載環境を確保するブランドセーフティ対策が重要視されています。
ビューアビリティとは
ビューアビリティとは、配信された広告のうち、実際にユーザーが視認可能な状態にあったインプレッションの割合を指します。一般的な基準では、「広告の50%以上が1秒以上表示される」ことがビューアブルインプレッションとされます。しかし、ページ下部にある広告が閲覧される前に離脱されるケースも多く、表示されていなくても課金対象となる問題があります。ビューアビリティは、この無駄な広告配信を可視化し、最適な広告掲載を実現する指標です。
アドフラウドの仕組み
アドフラウドの仕組みは、広告のインプレッションやクリックを不正に操作し、広告収益を詐取するといったものです。詐欺業者は、ボットや不正アプリを利用して人工的に広告の表示回数やクリック数を水増しし、広告費を騙し取ります。具体的には、①詐欺用サイトを作成し広告を出稿させる、②ボットやトラフィックエクスチェンジを用いて不正にアクセスを増やす、③広告主が虚偽の広告成果に対して費用を支払う、といった流れで行われます。これにより広告主は無価値なトラフィックに資金を消耗し、広告効果の測定も歪められるリスクがあります。
アドフラウドが広告主に与えるデメリット
アドフラウドは広告主に多大な損害をもたらします。最大の問題は、不正なインプレッションやクリックによって広告費が浪費される点です。また、広告成果が水増しされることで、効果のない配信に予算を割くことになり、正確なデータ分析が困難になります。さらに、不正なサイトに広告が掲載されることでブランドイメージが毀損し、ユーザーからの信頼を失うリスクもあります。加えて、誤った広告データが自動入札に影響を与え、最適なターゲティングが阻害されることにより、広告戦略の精度が低下し、経営判断の誤りを招く可能性さえあります。
アドフラウドの種類13選
①隠し広告
隠し広告は、ユーザーに視認されない状態で広告を表示し、インプレッション数を不正に水増しするアドフラウド手法の一つです。主な手法として、極小サイズの広告配置、透明広告の挿入、1×1ピクセルでの表示などが挙げられます。システム上は広告が表示されているため広告費が発生しますが、実際にはユーザーに訴求されておらず、広告主にとっては純粋な損失となります。CSSを悪用して仕込まれるため検出が難しく、被害の発覚が遅れるリスクが高いため、十分な対策が必要です。
②過度な広告領域
過度な広告領域は、検索スパムと組み合わせて広告のみが表示されるページへ誘導し、不正にインプレッション数やクリック数を稼ぐ手法です。検索結果では通常のサイトに見えるためユーザーが誤って訪問しやすく、広告だらけのページに遷移することで誤クリックを誘発します。この手法はユーザー体験を著しく損ねるだけでなく、広告主にとっても無駄な広告費の支出やブランド毀損のリスクを高めるため、警戒が必要です。
③広告スタッキング
広告スタッキングは、複数の広告を1つの枠内に重ねて配置し、ユーザーには最前面の広告のみを表示させる手法です。見えない広告もインプレッションとして計測されるほか、クリック時に背後の広告までクリックされたと判定されることがあり、不正に広告効果を水増しできます。ユーザーが違和感を覚えにくいため発覚しづらく、広告主にとっては、無駄なコストや誤ったパフォーマンスデータの蓄積につながるリスクが高い手法です。
④アドインジェクション
アドインジェクションは、Webページに広告主の許可なく広告を挿入する手法です。主な手法として、既存の広告に重ねて新たな広告を表示させることで、元の広告のビューアビリティを損なわせ、または広告が全くないページに不正に広告を挿入することがあります。この手法により、正当な広告収入が不正業者の手に渡り、広告主やユーザーにとってはリスクや不利益が生じます。
⑤クリック洪水
クリック洪水は、不正業者が大量のクリック情報を生成し、ユーザーがアプリをインストールするタイミングでその情報を紐付ける手法です。これにより、実際にユーザーが広告をクリックしていなくても、計測ツール上では広告経由の成果が発生したように見せかけます。クリック洪水では、マルウェアで不正に取得した端末IDを使用して、広告のクリック数を水増しし、広告主に誤った成果を報告します。これにより、広告主は本来のオーガニック成果を失い、無駄な費用を支払うことになります。
⑥ブラウザの自動操作
ブラウザの自動操作は、botを使ってブラウザを自動で操作し、広告のクリックやページ閲覧を偽装する手法です。これにより、ユーザーが気づかないうちに高単価の広告が表示され、クリックが行われます。botは、広告主のサイトへのアクセスやリターゲティング広告の表示も自動化し、広告費の無駄遣いを引き起こします。
⑦自動リロード
自動リロードは、広告枠のみを自動的に更新し、表示回数を水増しするアドフラウドの手法です。ページや広告のリロードを短期間で繰り返すことで、広告費を不正に請求します。特に、ユーザーのスクロールや動画の再生に合わせてリロードされるため、広告主にとっては無駄なインプレッションが発生し、サーバーへの負担も増大します。
⑧ドメインスプーフィング
ドメインスプーフィングは、正規のウェブサイトのドメインを偽装して、不正な広告オークションに参加するアドフラウドです。詐欺サイトに広告が掲載されることで、広告主は意図しないターゲットに広告を出稿し、ブランド毀損や信頼性の低下を招きます。この手法はツールを用いないと発見が難しく、企業イメージを損なうリスクが高いため、注意が必要です。
⑨ファーム(デバイスファーム)
ファーム(デバイスファーム)は「端末養殖場」とも呼ばれ、大量のデバイスやbotを使い、不正にアプリのインストールやクリック、広告表示を水増しする手法です。ボットやオペレーターが端末IDをリセットして複数の端末からの成果を偽装することもあります。広告主には無駄な広告費用が発生し、SNSの「いいね」やレビューなどのファネルコンバージョンにも悪影響を与えるため、深刻な損害を招く可能性があります。
⑩デバイス乗っ取り
デバイス乗っ取りは、ユーザーの端末に不正プログラムを感染させてデバイスを乗っ取り、強制的に広告を表示させたり、クリックさせてインプレッションやクリック数を水増ししたりする手法です。マルウェアにより、ユーザーが意図しないアクションを実行させ、広告費を不正に稼ぐことができます。この手法はユーザーの端末を直接操作するため、非常に厄介で悪質とされています。
⑪データセンタートラフィック
データセンタートラフィックは、データセンターやレンタルサーバーのIPアドレスから発生する不正アクセスを指します。通常、ユーザーのクリックは携帯回線やISPの回線を通じて行われるため、データセンターからのアクセスは異常であり、不正を見抜く手がかりとなります。ただし、近年ではこうしたトラフィックの隠蔽技術が進化しており、発見が難しくなってきています。
⑫インストールハイジャック
インストールハイジャックは、不正業者がユーザーの端末にマルウェアを感染させ、アプリストア内でのアクティビティを監視して偽クリックを作り出す手法です。ユーザーがアプリをダウンロードする際、マルウェアが介入し、不正な広告クリックを生成します。その結果、実際のインストールは不正業者の広告に紐付けられ、広告主に対して偽の成果が報告されます。
⑬SDKスプーフィング
SDKスプーフィングは、不正業者がSDK(ソフトウェア開発キット)を利用して、別のアプリの行動データを偽装し、アプリAで発生したイベントやクリックをアプリBで発生したかのように見せかける手法です。この手法では、アプリAに不正なコードを仕込み、アトリビューションツールに虚偽のデータを送信して広告成果を水増しし、広告主の予算を不正に搾取します。オープンソースSDKは特に脆弱で偽装が容易なため、注意が必要です。
アドフラウド4つの対策
①正しい知識を身につける
アドフラウドを防ぐ第一歩は、その手口や影響を正しく理解することです。広告詐欺は広告費の浪費にとどまらず、成果データを歪め、適切な施策判断を妨げるリスクを伴います。また、不正なインプレッションやクリックを見抜けなければ、成功している施策を無駄に見直し、さらなるコスト増につながる可能性があります。広告の成果を評価する際には、「これはアドフラウドでは?」と疑う視点を持つことが重要です。
②アクセスをモニタリングし、不自然な挙動に気をつける
アドフラウドを見抜くためには、アクセスデータの継続的なモニタリングが不可欠です。短時間で急激にアクセスが増加するIPや端末、不自然に短いCTIT(クリックからインストールまでの時間)、極端に高いアクティブ率などは、アドフラウドの兆候と考えられます。アクセス解析タグを適切に設定し、怪しい挙動を検出したらブラックリスト化し、広告配信を除外。クリック率や未払い注文の異常値もチェックし、不正サイトへの出稿を防ぐことが重要です。
③ホワイトリスト・ブラックリストを作成する
アドフラウド対策として、不正が疑われるサイトを「ブラックリスト」に追加し、広告出稿を停止することが有効です。未払い・不正注文が多いサイトや、不自然なトラフィックが発生するメディアを排除することで、無駄な広告費の流出を防ぎます。また、安全性が確認されたサイトのみをリスト化した「ホワイトリスト」を活用し、信頼できる媒体に限定して広告配信を行うことで、アドフラウドのリスクを低減できます。ただし、サイトの安全性は時間とともに変化するため、定期的なリストの更新が不可欠です。安価なインプレッションやクリックを優先せず、質の高いメディアへの出稿を意識してください。
④アドフラウド対策ツールを導入する
アクセス監視や出稿先の精査、ブラックリスト管理などの対策には時間とリソースが必要です。これらを効率化するために、アドフラウド対策ツールやアドベリフィケーションツールを導入する方法があります。これらのツールは、不正アクセスや異常なトラフィックを自動で検知・ブロックし、広告の健全性を保つとともに、人的コストの削減にも寄与します。ただし、導入にはコストがかかるため、被害額を試算し、費用対効果を考慮した上で導入を決定することが重要です。
まとめ
アドフラウド(広告詐欺)は、広告費の搾取だけでなく、データ分析を歪め、広告効果を著しく低下させる深刻な問題です。日本国内のアドフラウド発生率は世界トップクラスにもかかわらず、依然として多くの企業が十分な対策を講じていません。本記事では、代表的なアドフラウドの手口13種類を解説し、企業が取るべき4つの対策を紹介しました。アドフラウドは年々巧妙化しており、手動での対策には限界があります。リスクを最小限に抑え、正確な広告運用を行うためには、アドフラウド対策ツールの導入や、ブランドセーフティ・ビューアビリティといった包括的な視点でのリスク管理が不可欠です。